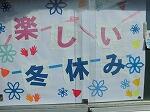校長室から
成長の中に
寒さの中にも春の訪れを感じる今日この頃です。様々な木をよく見ると、芽が出始めて、花を咲かせる準備をしています。
子ども達にとっては一年間のまとめとなる時期ですが、一日一日を大切にして、学級の友達や先生方と多くの思い出をつくってほしいと思います。
さて、3月は多くの活動の中で、いつもリーダーとして活躍していた6年生35名が卒業を迎えます。各学年が、6年生への感謝の気持ちや卒業をお祝いする気持ちを伝えようと準備を進めています。
6年生には、それらの思いをしっかりと受けとめ自信をもって松尾小学校を巣立っていってほしいと思います。今年度の6年生の学年スローガンは「挑戦」です。様々な活動の中で、自分たちの姿が松尾小学校の姿であるという気持ちをもち、下級生の道しるべとして素敵な姿をたくさん見せました。「何事にも前向きに取り組む」という力強いスローガンでした。この姿勢は、5年生にしっかりと受け継がれ松尾の伝統として根付いていくことと思います。
そのバトンを受け継ぐ5年生は、「ハーモニー」をスローガンとし、多くのことに「協力」した一年間でした。3月は、学校全体を見ながら「更に協力」し、4月からは、最高学年として松尾小学校をリードしていってくれるものと期待しています。その他の学年も、この一年、学級の目標に向かって、心を一つにして進んできました。その振り返りを行いながら、次の学年に向けて準備をしていきます。
3月は是非、御家庭でも卒業や進級を前にして一年間を振り返り、お子様の成長を一緒に喜んでいただけたらと思います。子ども達の成長には、一人ひとりの頑張りと努力が、そして、それを支えてくださったたくさんの人の励ましがあったことと思います。子どもたちの成長の中にあるその見えないものをしっかりと見つめさせたいとも思います。
残り少ない令和3年度ですが、変わらぬ御理解・御協力をよろしくお願いいたします。



2月を迎えました!
日差しも明るく、日も少し長くなったように感じます。
早いもので2月に入りました。コロナウイルス感染症が今後どうなるか気になるところではありますが、引き続き感染症予防に努めていきたいと思います。
さて学校では、「まとめの時期」に入りました。始まりがあれば、終わりもあります。子ども達は、学年の始めや学期ごとに目標を立てたことでしょう。目標の達成度はどうだったのでしょうか。
「初心忘るべからず」という言葉があります。これは世阿弥が考えた言葉で、今では「最初の志を忘れてはならない」という意味で使われています。しかし、世阿弥が意図とすることは少し違っていたようです。「初心を忘れるな」とは、人生の試練の時に、どうやってその試練を乗り越えていったのかという経験を忘れるなということだそうです。
これから子ども達が成長していく過程には、様々な試練が待ち受けています。そんなとき助けになるのは、家族や友人、まわりの人々、そして、自分です。今まで自分が経験してきた試練をどう乗り越えたのか、それを思い出せるかどうかが重要なポイントではないでしょうか。
今年度も残り2か月、生活や学習をまとめる上で、分からないこと、忘れたこと、できなかったこと等をもう一度振り返らせ、確実なものにさせていきたいと考えます。
保護者の皆様には、変わらぬ御理解と御協力をお願いいたします。
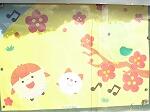


避難訓練
1月13日(木)に避難訓練を行いました。
避難訓練は疑似体験ではありますが、いざという時に適切な行動を取ることができるように経験を積むものです。そして、自分の命を守るための重要な行事です。
子ども達の避難する様子を見ていて、あわてて避難する子どもやふざけて避難する子どもが一人もなく、それぞれが真剣な態度で避難できたのは大変よかったと思います。また、「おさない」「かけない」「しゃべらない」「もどらない」という「お・か・し・も」の約束を守って避難できました。
人間は経験をすることによって、行動の仕方を学びます。子ども達も、避難訓練を繰り返し行うことによって、その効果が期待できることでしょう。
予知の技術が進歩したとはいえ、天災はまだまだ「いつ」「どこで」「どの程度」の天災に遭遇するか分かりません。火災等の人間に起因する人災も予測できません。また、「地震・火災」の他にも「津波」「強風」「河川の増水」そして、それに伴う停電・浸水など多岐にわたる危機管理が要求されるようになったとつくづく思います。
私たちは災害をついつい他人事のように感じてしまいがちです。しかし、この新型コロナウイルス感染症についても、こんな状況になるということを想像していたでしょうか?
御家庭でも、いざという時の準備、「心の準備」、「物の準備」、家族との「連絡の準備」等、共有事項を話し合ってほしいと思います。



令和4年(2022年)のスタートです!
いよいよ令和4年(2022年)、新しい一年が始まりました。
新型コロナウイルス感染症については、厳しい状況が今後も続いていくことが予想されます。しかし、悲観ばかり、不安ばかり、心配ばかりしていても何も始まりません。しっかりと前を向いて力強く進んでいきたいと思います。新しい年はスタートし、ひと時も休むことなく、時を刻み、進んでいきます。令和4年が全ての人々にとって、輝かしく幸せな一年になりことを願ってやみません。
さて、学校は、いよいよ3学期を迎え、各学年とも締めくくりの段階に入りました。子ども達はこの節目のなかで、「今年こそは」と新しい年の夢を描いたり、目標を立てていることでしょう。夢や目標は、1年生にとっても、卒業を前にした6年生においても、その後の成長に重要な役割を果たします。
この3学期は、1年間の総まとめの時期として、次の年度に確かにつなげる力を育てることを大切にしていきたいと思います。
また、今年は新しい校舎の完成とともに、教育環境が大きく変化する年となります。
教育には、「不易と流行」という言葉がよく使われています。これは、松尾芭蕉の弟子が書いたものの中に、芭蕉の言葉として残されたものからできた言葉です。「不易」とは「時代を超えてもずっと変わらない価値のあるもの」のことで、「流行」とは「その時々の時代の変化に合わせて変えていくもの」のことです。そして、その両方が大切だとしています。つまり、「不変の真理を知らなければ基礎は確立せず、変化を知らなければ新たな進展がない」ということです。
教育環境が変化していく年だからこそ「不易と流行」に目を向け、先を見据えながらも、何が大切なのかを十分に吟味して、変化を恐れず必要なことを実践していく、そんな年にしていきたいと思います。
一日一日を大事にしながら、子ども達の夢や願いを実現させるための力を付けられるよ
うに、令和4年も教職員一同、努力して参ります。保護者の皆様、地域の皆様、関係者の皆様には、今年も変わらぬ御理解と御協力をよろしくお願いいたします。



2学期、御協力ありがとうございました!
本日、2学期の終業式を迎えました。
保護者・地域の皆様には、学校教育活動への御理解・御協力、本当にありがとうございました。
2学期は、季節が夏から秋へ、そして冬へと変わっていった学期でした。この季節の移り変わりと同じくらい、どの子ども達も様々な部分で確実に変化・成長したことと思います。
さて、人は年齢分の「1」の大きさで変わっていくということを聞いたことがあります。例えば2歳の子どもは、1歳から2歳にかけて「1/2」も変化するということです。半分も変わってしまう・・・。そう言えば、私の子どもが歩けるようになったり、話せるようになったりした時が1歳頃から2歳だったことを思い出します。
ちなみに、私は58歳ですから「1/58」の変化をするということになります。正直言って、変わったところを探すのが大変です。しかし、変化は成長ですから、いくつになっても確実にどこかは成長しているのかなと思います。
こう考えていくと、低学年の子どもの方が大きく変化をしますから、低学年の経験は大切なことだと気づかされます。また、人生100年時代を生きる子ども達にとって、小学校生活はその基礎をつくる大切な時期と考えられます。できなかったことも必ずできるように変化をする時期が、小学校から中学校にかけての年代ということになります。
個人面談では、子どもの全ての成長の様子や課題をお伝えすることはできませんでしたが、2学期のノート、製作したもの、作文、テストなどを一緒に見返しながら、「できたこと」「できるようになったこと」「前よりも良くなったこと」を大いにほめてあげていただきたいと思います。そして、次に頑張ることも一緒に考えてほしいと思います。それが新年の目標になるよう、お家の方と一緒に決めてみてください。
冬休みは家庭で過ごす休みです。年末年始での日本文化に触れる休みです。お手伝いがたくさんある休みです。お金をもらうことが多い休みです。家族でいろいろなお話をし、家族でお手伝いで助け合い、家族でお金を使うルールを決め、子どもにとっての1/〇の大きな変化と共に、しっかりと心に刻まれる年末年始休みを過ごせることを願っています。
1月6日には、さらに成長した姿で元気に登校してくれることを楽しみにしています。
皆様、よいお年をお迎えください。