校長室から
熱中症事故防止・対策、体育の授業におけるマスク着用について
令和2年度には、全国の学校の管理下において3,000件を超える熱中症事故が発生しています。また、運動を行う際にマスクを着用する場合、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリスクも指摘されています。
これからの季節、学校では、以下の点について再度確認し、新型コロナウイルス感染症予防と熱中症予防を両立させていきたいと思います。
保護者の皆様も体調には十分気をつけてください。
1 熱中症予防
(1)暑さを避ける。(涼しい服装、エアコン・サ-キュレーターの活用)
(2)こまめに水分補給をする。(のどが渇いていなくても水分補給)
(3)暑さに関する情報を確認する。(暑さ指数・熱中症警戒アラート等)
(4)授業内容や気温上昇により熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、喚起や児童の間に十分な距離を保つなどの配慮をした上で、マスクを外す指示をする。
(5)児童本人が暑さで息苦しいと感じた時などは、マスクを外したり、一時的に片耳だけにかけて呼吸をしたりするなど、本人の判断でも適切に対応できるように指導する。
2 体育時におけるマスクの着用
運動時のマスク着用による身体へのリスクを考慮して、学校の体育の授業におけるマス クの着用はさせないが、体育の授業における感染リスクを避けるためには、地域の感染状況を踏まえ、児童生徒の間隔を十分に確保するなど、次の事項を十分に踏まえた対策を講じる。
(1)児童が集合・整列する場面を少なくし,身体的距離を確保する。
(2)用具の使用後の消毒や授業の前後に手洗いを徹底する。
(3)見学者にはマスクを着用させる。
(4)児童が教え合う場面では互いの距離を確保するとともに、児童に不必要な会話や発声を行わないよう指導する。
なお、すべて「必ずマスクを外さなければならない」という指導ではなく、児童がマスクの着用を希望する場合は、マスクの着用を否定するものではありません。ただ、マスクの着用時に運動や活動を行う際には、呼気が激しくなるような運動や活動を行うことを控えたり、児童の呼吸が苦しい様子が見られる場合は、必要に応じてマスクを外し、他の児童との距離を確保して休憩するよう指導します。
御理解御協力をよろしくお願いします。
※参考 文科省・スポーツ省・山武市教育委員会マニュアル


1学期の中間地点
季節が春から梅雨へ、そして夏へと変わる1学期の中間地点です。子ども達も、新しい先生や環境に慣れて、本来の自分を発揮しています。
さて、アメリカの安全技師ハインリッヒが安全に関して発表した「1:29:300」という法則があるのを御存じでしょうか。
それは「1件の大きな事故や災害が発生する背景に、29件の小さな事故や災害、300件のヒヤリハットがある」という警告として、安全活動の中で多く採りあげられているものです。「ヒヤリハット」とは、事故になってもおかしくなかった状況を「冷や汗をかく…ヒヤリ」「声も出ず息をのむ…ハット」で表した造語です。
では、このハインリッヒの法則から何を学ぶことができるでしょうか?
1件の大きな事故を防ぐためには、「ヒヤリハット」の段階で注意すること、見逃さないことが、29件の小さな事故や災害も防ぐことができるということです。
〇階段をおりるときに少し上から飛び降り、けがをしそうになった。
〇廊下を走っていて、ぶつかりそうになった。
〇自転車の速度を出しすぎて、転倒しそうになった。
〇安全確認せず道路を横断しようとした時、自動車が来ていた。 等
これくらいは大丈夫だろうと安易に思ったことが大きな事故につながります。
松尾小学校では、6月の教育活動を更に充実させるために「落ち着いた生活・学習態度」を念頭に指導・支援にあたっていきます。子ども達からの訴えや先生方が気付いたこと、保護者や地域の方々からの相談や報告をヒヤリハットとして受け止め、全職員で情報の共有をして重大事故を起こさないようにしていきます。
家庭・地域の見守りと声かけもどうぞよろしくお願いします。
※学校では、様々な植物を育てています。






掃除も大切な学習時間!
海外の国々では児童に学校清掃をさせることは多くありません。これは、ほとんどの国にとって清掃は「作業・職業」であり、「学習内容」ではないためだとされています。世界105カ国を調査した出典によると、児童生徒が掃除を行う国は34.3%、清掃員に掃除を任せる国は58.1%となっています。
例えば、アメリカでは大部分の学校で清掃員が学校清掃を行っています。これは「作業を清掃員に任せることで児童生徒が本分に集中できる」という考え方にもとづいており、児童生徒自身が学校を掃除するべきという考え方は主流ではありません。その一方で、生徒がゴミを拾わない、机にチューインガムが貼り付いているなどの、生徒に掃除をさせないゆえの問題点も指摘されています。これは決して児童生徒に常識が無いということではなく、「掃除をする人の仕事を取ってはいけない!」と言われて育ったという背景もあります。このような現状から、児童生徒による学校清掃を取り入れるべきだという声も増えているようです。
そのような状況に対して、新たに学校清掃を導入した国がシンガポールです。従来はアメリカと同様に清掃員を雇うことが一般的でしたが、2016年に生徒に毎日の清掃を義務付ける政策を実施しました。シンガポールの教育省MOEは、「日本や台湾にならって学校清掃を導入した」と明言しています。この政策に対する国民の反応はさまざまで、「子どものしつけになる」「経費削減になる」と賛同する人もいれば「勉学に支障が出る」「雇用が減る」と懸念を示す人もいるようです。
では、日本は当たり前のように根付いている学校清掃の文化は、どのようにして始まったのでしょうか。その起源だとされる要因は大きく2つあります。1つは剣道、柔道、華道、茶道などの「道」の存在で、もう1つは仏教です。
剣道や柔道の経験者なら分かる人も多いと思いますが、武道の世界では稽古場をきれいに保つことをとても大切にしており、稽古の前後には必ず道場を掃除することで心を磨くとされています。
また、仏教の修業は「一に作務、二に勤行、三に学問」といわれています。そして、一の作務の代表的なものが掃除です。このことから、僧侶の修行においてはお経を読んだり勉強をしたりするよりも掃除のほうが優先順位が高いということが分かります。
これらによって仏教や各武道などが古くから盛んだった日本では学校清掃が当たり前となり、自分の場所を自らの手できれいにすることを学ぶようになったようです。
日本人が協調性や思いやりを高く評価されるのは、学校清掃による学びのおかげもあるといえるでしょう。学校で児童が取り組む掃除時間は1日に15分。しかし年間で考えると約60時間。教科に相当する時間にもなります。
自分の手で学校の掃除を行うというとても小さな一歩から、自分の使う場所を綺麗に保つ・物を大切にする気持ち、一つの事を他者と協力してやり遂げる協調性、自分が卒業したあとに同じ場を使う他者を思いやる気持ちを、この時間から有効に学ぶことを期待します。



ルールからマナーへ
学校生活を送る上で「きまりを守る」ということがあります。社会にルールがあるように学校にも様々なきまりや約束があります。
「きまりを守りなさい」とよく言われますが、何のためにきまりがあり、なぜそれらを守る必要があるのでしょうか。また、きまりを守るために必要なものとは何でしょうか。
きまりや約束は、学校という集団生活の場で、お互いが気持ちよく過ごせるようにするためにあります。それらを守らないと、周りに迷惑をかけてしまいますし、それが、やがては自分に返ってきます。学校は、きまりを守ったり、たくさんの人とかかわったりしながら社会性を身に付ける場でもあります。
子ども達を見ていると「先生が言ったから」「きまりを破ると怒られるから」といった受け身な考えでいる子どももいます。しかし、初めは受け身な考えでいても、繰り返し失敗を克服していくなかで、「お互いが気持ちよく生活すること」また「自分自身の判断が大切」ということを学んでいくはずです。そのためには、大人が良い行いを褒めたり、失敗したら何がいけなかったのかを一緒に考えたりすることが必要です。失敗と成功の体験の積み重ねが心を育て、判断力を育てることにつながります。このことは学校だけ、家庭だけでできるものではありません。力を合わせてじっくりと時間をかけ、継続していくことが大切です。
松尾小学校では、「無言清掃」「サイレントゾーン(静かに歩く)」「ノーチャイム」等の取組みも2年目になり、成果を上げています。「やればできる」子ども達です。これからも、子ども達にはその他様々なきまりや約束を守ることをとおして、みんなが気持ちよく生活できるように、また自分自身が正しいことをしていると判断できるようになってほしいと思います。
「おしゃれは自分のため、身だしなみは他人のため」という言葉があります。ルールは守らなければならないという他律という面もありますが、マナーはきまりというよりは相手への思いやりが優先し、自律的で豊かな集団生活、社会生活へとつながります。
ルールを守るだけでなく、望ましいマナーを身に付けた大人になることを願います。
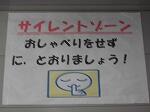
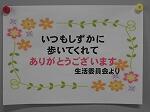
新年度がスタートして1か月
22日(木)から始まりました家庭訪問も過日終えることができました。お忙しい中、お時間を取っていただき本当にありがとうございました。家庭訪問でお聞きしたお子様の様子やご要望等を教職員で共有しながら、この一年間、子ども達が楽しく充実した学校生活を送ることができるよう、全力で指導していきます。
また、新年度がスタートして1か月が過ぎようとしています。子ども達も進級したばかりの緊張した時期を終え、新しい学年に慣れ始めた頃ではないかと思います。明日からの5連休を楽しく安全に過ごすために、連休中の過ごし方について、学校では以下の指導を行いました。御家庭でも重ねてお声掛けいただき、子ども達の意識を高めていけるよう、御協力をお願いします。
〇コロナ感染防止のため、手洗い、マスクの着用、3密回避をする。
〇健康な生活・規則正しい生活を送る。「早寝、早起き、朝ごはん」
〇安全な生活・自転車の乗り方等、交通安全に注意する。 等
連休明けに全員の元気な顔を見せてください。
※千葉県人権の花(しゃくやく)が満開を迎えようとしています!!

人権の花運動
この運動は、おもに小学生を対象とした啓発運動で、昭和57年度から実施されています。その内容は、学校に配布した苗木、種子、球根などを、子ども達が協力し育てることによって生命の尊さを実感し、その中で豊かな心を育み、優しさと思いやりの心を体得することを目的としたものです。







