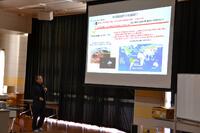文字
背景
行間
校長室から
1月8日 避難訓練
今回の避難訓練は、いつものように「2時間目に避難訓練をします」というような予告はなく、昼休みに「訓練、訓練、地震発生。すみやかに頭を守り、揺れが収まるまで待ちましょう」という全校放送が入って避難するという訓練でした。この放送後、続けて「訓練、訓練、職員室前から火が出ました。西階段を使わず、素早く避難しなさい」と全校に指示が出ました。いつもならば、先生方がそばにいて避難指示を出し、一緒に逃げるという訓練ですが、今回は自分で考えて行動するための訓練でした。
子ども達は、グラウンドで遊んでいたり、廊下や教室にいたりとそれぞれの場所で放送を聞きました。落ち着いて行動ができるかと心配でしたが、日ごろの訓練や先生方からの指導を活かし、4つの約束「おさない、かけない、しゃべらない、もどらない」を守り、無事に避難することができました。この4つの約束は、自分だけでなく、周りの人の命も守ることにつながります。
災害はいつ起こるか分かりません。大人がいない時でも「自分はどう動けば命を守れるか」を考えて行動できる力が必要です。今日の訓練を練習に終わらせず、いざという時に命を守る行動ができるように、引き続き、指導していきたいと思います。
1月7日 3学期始業式
あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い致します。
いよいよ一年間のまとめの3学期が始まりました。3学期は短いですので、充実した期間になるように、始業式では、校長からは次のような話をしました。なお、Zomにて各教室をつなぎ、行いました。
【校長の話(抜粋)】
今年は午年です。馬は元気いっぱいに、前に前にと一生懸命に走る動物です。馬には、走るための蹄(ひづめ)があります。蹄があるから、しっかり地面をけって前に進むことができます。では、みなさんが前に進むために持っている「蹄」は何でしょう。それは夢中になる気持ちです。「楽しい!」「もっとやりたい!」と思う気持ちが、みなさんを進ませてくれます。勉強でも、運動でも、何か一つ、夢中になれることを見つけて、取り組みましょう。
さて、蹄はUの字の形をしているので、幸せを入れて、逃がさない形だと言われています。そのため、蹄には「幸せを運んでくる」「福を集める」という意味があります。また、昔から「笑う門には福来る」という言葉がありますが、「笑顔のあるところに、幸せはやってくる」という意味です。“笑顔であいさつをする。友だちを応援する。失敗しても「大丈夫だよ」と声をかける。”そうやって笑顔があふれる学校には、楽しいことやうれしいことが、たくさんやってきます。
3学期は1年間のまとめの学期です。夢中という蹄で一歩一歩前に進み、笑顔いっぱいの学校をつくっていきましょう。
12月24日 2学期終業式
2学期の終業式を無事に迎えることができました。1学期の始業式ぶりに体育館に集合して行いました。まず、全校で校歌を歌いましたが、その歌声のすばらしさに感動しました。伸びやかで大きな声が体育館中に響きわたり、その歌声は児童の成長を物語っているようでした。
次に校長からの話でした。その中で、2学期の頑張りを褒め、冬休みに守って欲しいこと、取り組んで欲しいことを3つ話しました。それは、自分の命は自分で守ること、2学期につけた力を家庭学習で持続すること、身近な人に思いやりの心をもって接することの3点を伝えました。
その後、生徒指導主任と5年生の子ども達が前に立ち、「あいうえお」作文で安全な冬休みの過ごし方について全校に呼びかけました。12日間の冬休みを安全に楽しく過ごし、3学期に笑顔で会えることを楽しみにしています。よいお年をお迎えくださいませ。
12月22日 スリランカ洪水被害への支援について
スリランカでは、先月起こった大雨で、壊滅的な洪水や土砂崩れにより大きな被害が発生し、非常事態宣言が出されました。これを受け、本校にはスリランカ出身のお子さんが多いことから、衣類と文房具を支援物資としてスリランカの子ども達に届けたい旨を呼びかけたところ、多くのご家庭からご寄付をいただきました。これらは手順を踏んで、スリランカへ届けたいと思います。ご協力、ありがとうございました。
12月18日 三神泉先生 ご来校
「すばる望遠鏡」の開発に携わり、世界的な天文プロジェクトを成功に導かれた三神 泉 先生をお迎えし、ご講演をいただきました。
三神先生は、昭和30年に宮城県にお生まれになり、古川高等学校を卒業後、東北大学へ進学されました。大学卒業後は三菱電機株式会社に入社され、技術者として活躍されました。その後、ハワイ島に建設された「すばる望遠鏡」の開発において、プロジェクト部長を務められ、世界最高水準の望遠鏡の完成に大きく貢献されました。NHK「プロジェクトX」でも紹介され、三神先生はそのご功績により紫綬褒章を受章されています。
ご講演では、宇宙や望遠鏡のお話だけでなく、「夢を持ち、仲間と協力しながら挑戦し続けることの大切さ」について、子どもたちに分かりやすくお話しくださいました。児童たちは、世界で活躍する技術者の言葉に目を輝かせながら耳を傾けていました。
ご多用の中、兵庫県宝塚市より本校のためにお越しいただいた三神先生に、心より感謝申し上げます。